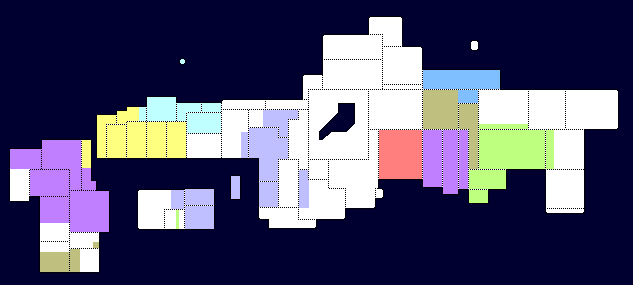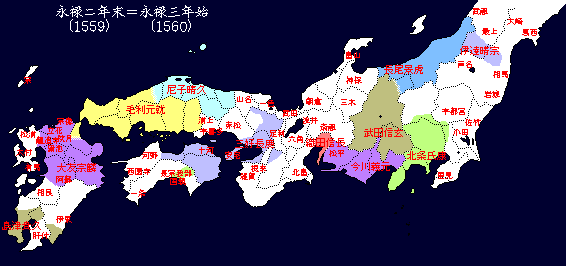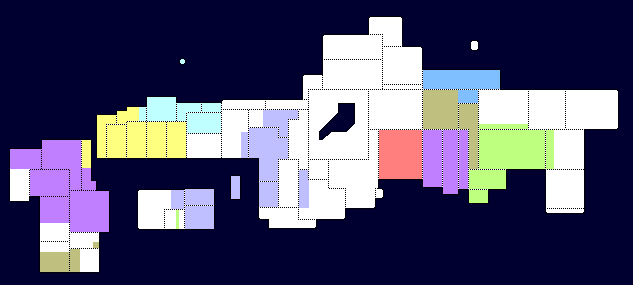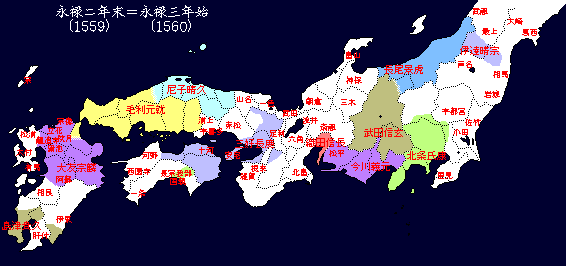|
永禄三年(1560)
(西日本)
大内氏倒れ、中国を毛利が、九州を大友が継いだ。その結果大友は肥前にも進んだが、
その間毛利が尼子を抑えつつ、九州・豊前に進出する。
大内は消えたが、大友・毛利・尼子の勢力に置き換わった。
(中央)
一時京都から逐われていた将軍義輝を再び京都に迎えた。
政権運営上の都合があったのだろうが、
信長と義昭の関係との比較ができる後世の目から見れば、中世勢力との妥協とすら見える。
しかし将軍家との妥協後も畿内各国への浸透は続いているのだから、長慶存命中は
正解と思える選択肢だったろう。
(東日本)
信長による尾張統一により織田家も再びプレイヤーに加わる。
織田と今川、武田と上杉(長尾)それぞれ勢力均衡しているように見える。
北条のみ悠々と関東経営しているようにさえ見える。
しかし桶狭間では今川軍30,000に対して織田軍2,000といわれる。
それぞれの実効支配の程度を示すものであろう。
信長が新しく征服した将兵の動員をかけなかったこともあるだろう。
巷間言われるように、そんなに国力に差があったかなとも思う。
むしろ義元没後、今川が尾張に再征できない原因として国力の差のなさがでたと
解釈できるのだろうか
一方、謙信も関東に進出する。信玄と勢力均衡しているだけのはずなのに、
その上をいく北条に真っ向挑んでいく。関東管領という中世的権威の残滓がまだある
といえよう。
|