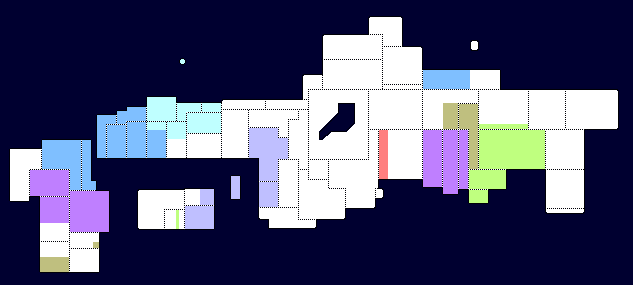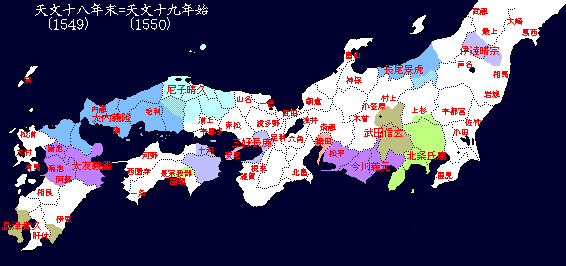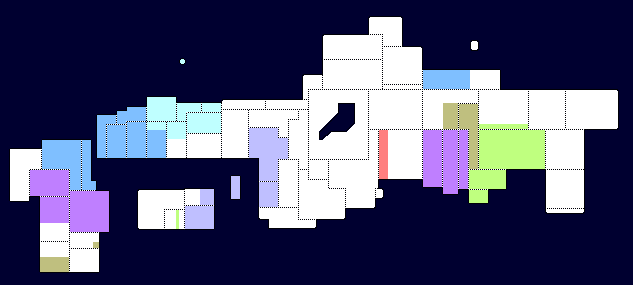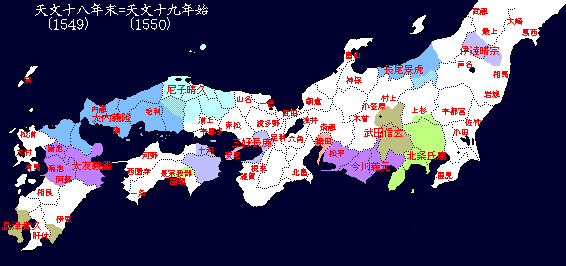|
天文十九年(1550)
(西日本)
名族少弐氏滅亡したが、九州方面異常なし。大内・大友が均衡していたといえるのか。
そのためか肥前がここでは草刈場になっていない。
反面、中国方面も大模様の変動はない。備後への大内の浸透がある程度。これが毛利氏の実力涵養になったとされる。
(中央)
三好長慶、細川晴元を政権から逐う。石高倍になったが、他勢力から一頭抜きん出た大勢力というわけではない。
地理的にたまたま京洛に近い、自身細川政権に属す身であったなど、後年の織田政権との違いは明瞭
(東日本)
織田信秀、松平広忠の死により、今川・織田の勢力比は圧倒的に今川有利となる。
尾張のポテンシャルを思うとき、ここで今川が尾張を取れなかったことによる日本史への寄与は計り知れない。
尾張半国でも取ってからの戦いならば、もう勝負ありだったかもしれない。
もっともこの時点では尾張守護斯波氏は延命しており、尾張侵攻は名分がなかったのかもしれない。
また均衡が破れたといえば、北条氏が大国武蔵を得、東日本最大の大名となった。
しかしこれ以後、下総一国のみを拡大するにとどまる。
後年、信玄・謙信と争うことになるが、ポテンシャルの点で別の仕様もあったようにも思う。
|