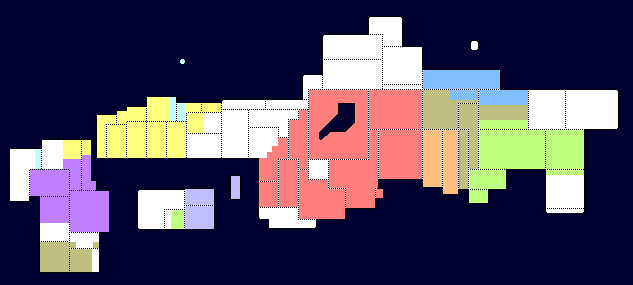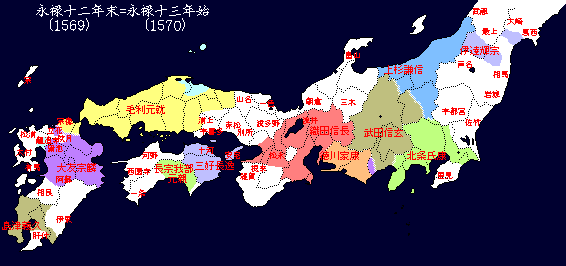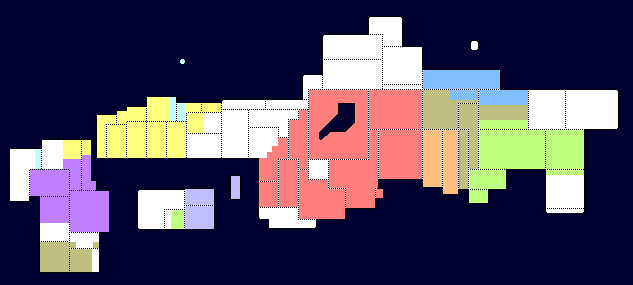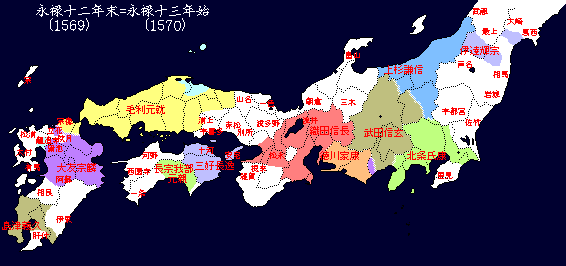|
元亀元年(1570)
(西日本)
二大勢力毛利・大友の抗争により、双方が背後を脅す。大友家は旧大内、旧少弐の諸族の裏切り、毛利家には尼子家の再起がある。
その恩恵か龍造寺氏が勃興し始めている。島津氏も薩隅を固めて北上の動きを始める。
三好氏は四国に逐われ畿内への再起を図るが、足元から土佐の新興大名・長宗我部氏が食いつき始めている。
しかし土佐の生産力の低さは如何ともしがたい。
(中央)
細川・畠山・六角といった近在勢力でなく、長躯尾張から上洛。
新たな権力者がそれまでに上洛した大名との違いは、尾張、美濃、伊勢、近江を支配し、400万石を背景にしていることにある。
圧倒的な第一位であり、かつ畿内・北陸に成長余地としてのフロンティアがあるといえる。
良く言われていることであるが、周囲に敵を抱えながら周囲の同時攻撃がなかったことにより、生産力で他を圧倒したといえるのではないか
(東日本)
この時期、今川家の扱いをめぐって、武田氏と北条氏が対立。これも信長に幸いしたといえる。
北条氏からすれば、謙信・信玄の来襲をともに小田原城で迎え撃つが、そのため上総、下野、常陸等を攻略できず、拡大できなかったことになる。
西日本にせよ、東日本にせよ、均衡状況があることが信長に幸いしたといえるだろう。
石高で対抗するならば、北条・武田・上杉が束になって始めて織田勢と等価となる。
|